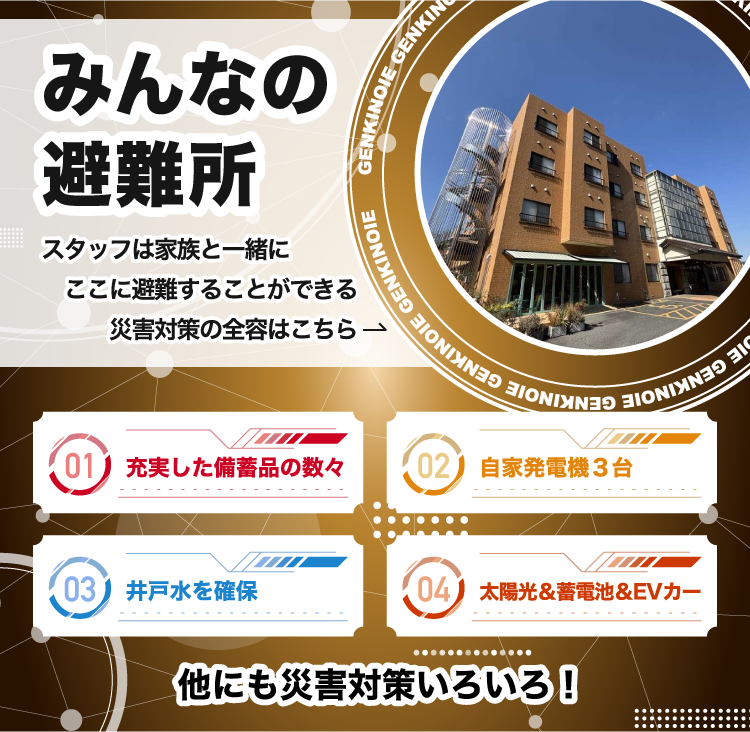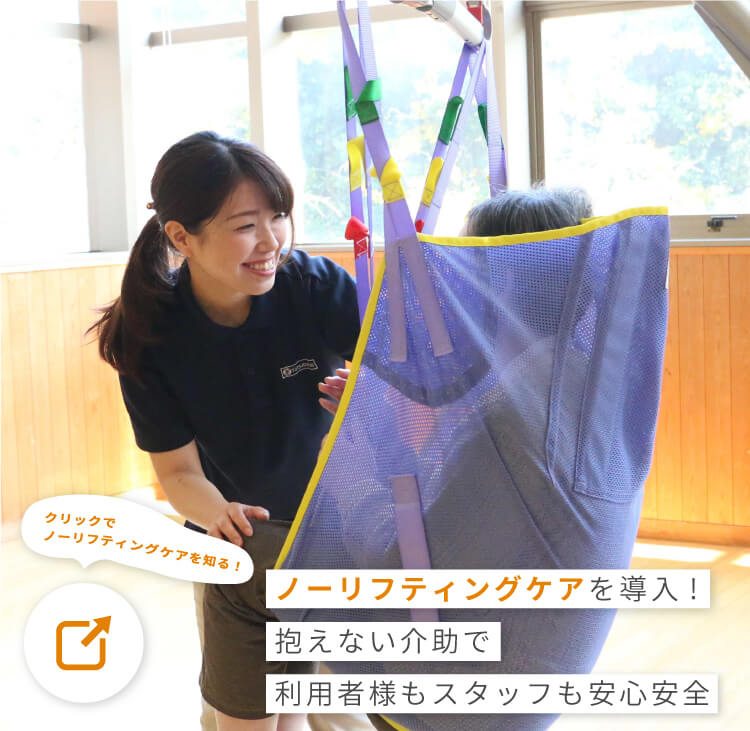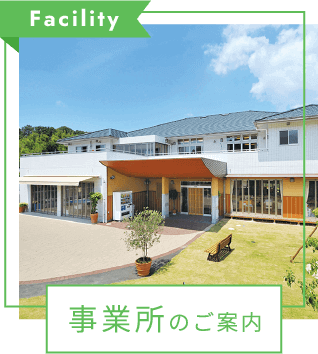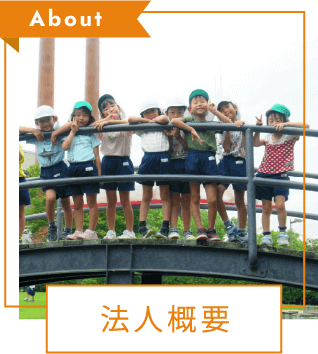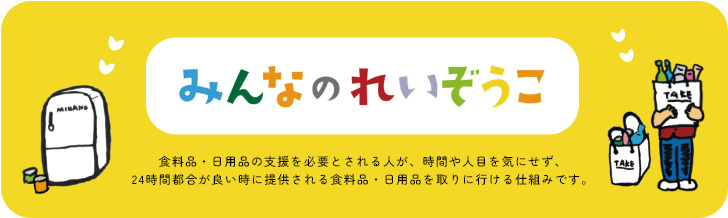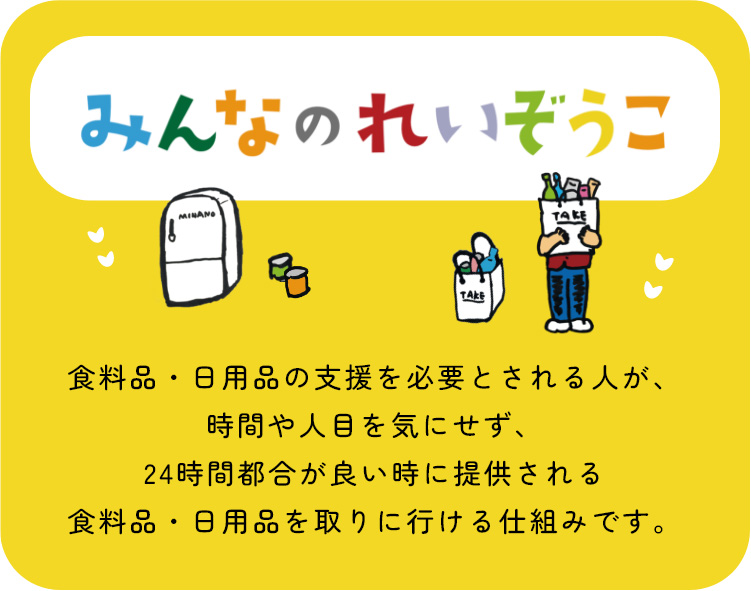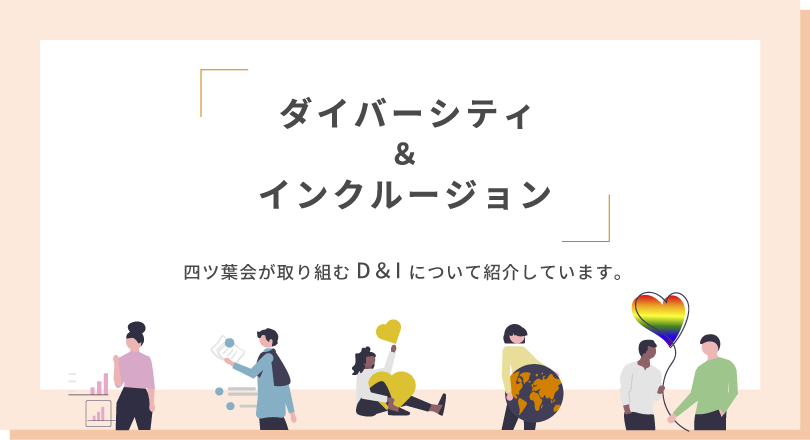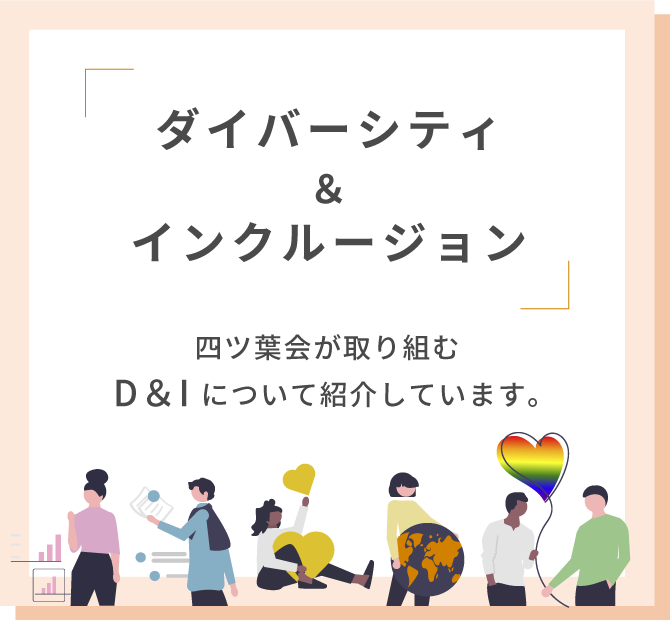Report活動報告
各施設の活動報告などを随時更新しています!
-
高齢者福祉部門
#外出しまくる特養
元気の家
2025.07.05
-
高齢者福祉部門
#外出しまくる特養
元気の家
2025.06.24
-
高齢者福祉部門
#イベントしまくる特養
元気の家
2025.06.15
-
高齢者福祉部門
#イベントしまくる特養
元気の家
2025.06.13
-
高齢者福祉部門
#イベントしまくる特養
元気の家
2025.05.23
-
高齢者福祉部門
#外出しまくる特養
元気の家
2025.05.20
-
高齢者福祉部門
#イベントしまくる特養
元気の家
2025.04.25
-
高齢者福祉部門
#元気を創るデイサービス
杉の子デイサービスセンター
2025.04.15
-
高齢者福祉部門
#利用者さんが働くデイサービス
杉の子デイサービスセンター
2025.04.02
-
高齢者福祉部門
#外出しまくる特養
元気の家
2025.03.27
-
障がい福祉部門
ちからの練習‼︎
もくもく
2025.06.21
-
障がい福祉部門
ミックスジュース作り🍹
これから・ICHIGO WORKS
2025.06.19
-
障がい福祉部門
ぶんぶんごま作り
れっつ
2025.06.17
-
障がい福祉部門
6月の制作活動
れっつ
2025.06.13
-
障がい福祉部門
避難訓練をしました
もくもく
2025.05.31
-
障がい福祉部門
いちごが実りました🍓
これから・ICHIGO WORKS
2025.05.27
-
障がい福祉部門
パフェ作り
れっつ
2025.05.23
-
障がい福祉部門
キネティックサンド
れっつ
2025.05.12
-
障がい福祉部門
交流会☆2025☆
もくもく
2025.04.29
-
障がい福祉部門
こいのぼりを作ったよ🎏♪
れっつ
2025.04.28
-
児童福祉部門
夏祭り☆彡
杉の子第二保育園
2025.07.11
-
児童福祉部門
☆6月の保育の様子②☆
すぎのこ認定こども園
2025.07.10
-
児童福祉部門
☆6月の保育の様子①☆
すぎのこ認定こども園
2025.07.10
-
児童福祉部門
保育の様子(0歳児)
杉の子第二保育園
2025.07.03
-
児童福祉部門
歯科検診
杉の子第二保育園
2025.07.03
-
児童福祉部門
7月休日講座
すぎのこ認定こども園
2025.07.02
-
児童福祉部門
☆1.2組 親子遠足の様子☆
すぎのこ認定こども園
2025.06.26
-
児童福祉部門
遠足(1.2組)
杉の子第二保育園
2025.06.06
-
児童福祉部門
保育の様子(1.2.3組)
杉の子第二保育園
2025.05.30
あなたの個性を仕事に活かす
職員ひとりひとりの思いや知識、
得意なこと、やりたいこと、
キャリアプランなどの
個性を尊重し、自分を活かしながら
やりがいを感じられる
施設を目指しています
ICHIGO WORKS
エラー: ID 3 のフィードが見つかりません。
アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。

@11111works